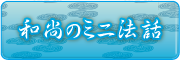和尚のミニ法話
門松と七五三
今年は暖冬傾向で、もうすぐお正月という気分にはなかなかなれないのですが、例年のように、また今年もNさんとHさんから門松を立てていただきました。地域子供会で作った後の流れで、光照寺の分もつくっていただきました。すごく立派ですばらしい出来栄えです。Nさんは30基余もつくられるそうですがそのほとんどが報酬をあてにしないボランティアだそうです。真似のできないことです。本当にありがとうございました。
さて、その門松の土台にコモが巻かれていますが、コモに巻く縄の本数をご存じでしたか。下から7本、5本、3本です(写真では確認しずらいですが)。七・五・三ですがきっと何か意味があるのでしょうね。
七五三と言えば子供の成長を願った神社へのお参りごとですが、お寺にも「七五三」はあるんですよ。ちょっと専門用語なので坊さんにしかわからないことなのですが、法要の開始に本堂内にある半鐘(殿鐘でんしょうと言います)を打ちますが、この数が7・5・3なのです。
まず中・中・小・大と4声打ちます。これを「打ち出し」と言います。第一会目は、カーン、カーン・・・と7声打ってからカンカンカン・・・・と速く打ちます。本堂内の準備ができたという合図です。第二会目は、カーン、カーン・・・と5声打ってから同様にカンカンカン・・・と速く打ちます。僧衆が出てきて導師を迎える準備ができたという合図です。第三会目は3声打ってから速く打ち上げます。導師が入堂する準備ができたという合図です。
ことこのように七五三は坊さんにも縁のあることなのです。(一般の方からすると、それで? なのでしょうが・・・)
おもしろうて やがて悲しき シルバー川柳
三条市シルバー人材センターの「生涯現役カレンダー」が各戸に配布されました。毎月のカレンダーにシルバー川柳が一句ずつ載っていました。いずれはシルバー世代に仲間入りする身としては「おもしろうて やがて悲しき」でした。いくつか紹介します。
〇年賀状 出さずにいたら 死亡説 (島根県47歳女性)
「たよりのないのはよい知らせ」は若い人のことで、シルバー世代は違うんですね。
〇マイナンバー ナンマイダーと 聞き違え(山梨県67歳男性)
単純におかしくて吹き出してしまいました。宗教法人にもマイナンバーがあるんですよ。この先、お寺もびっちりと管理されるのでしょうか。
〇俺だって 死ねば弔辞で 褒められる(千葉県72歳男性)
弔辞を読んでもらえる葬式ができるかどうか。最近は弔辞のないほうが圧倒的に多いですので、多くの人は褒められることのないまま旅立つことになるのでしょうか。通夜法話にはこの役も担っていると思っています。
あじさいが見頃です。
庫裡の玄関に鉢植えのあじさいをたくさん並べました。見頃です。
あじさいも品種改良が進んでいてさまざまな種類があるようです。並んでいるのは、「万華鏡」「ウエディングブーケ」「ピーターパン」「ダンスパーティ」「シュガーホワイト」「アリラン」・・・等々。品種名の不明なものもあります。挿し芽をしてたくさん増やしました。どうぞ見に来てください。
あじさいは七変化というとうり、土壌によって花の色が変化します。買ってきたときは赤色だったのに、挿し芽で増やしたら紫色になってしまったり、鮮やかな青色だったのにくすんだ色になってしまい見ごたえがなくなったりと、なかなか難しいものです。
今年もすでに挿し芽作業を行っています。来年はもっとたくさんのあじさいで囲まれた寺にしたいと思っています。
お寺にあじさいは似合いますよね。
7月12日の「松尾与十郎忌法要」においでの方に、あじさいの挿し木苗(2年もの)をプレゼントいたします。
3.11 菩薩に出会う
今日は3月11日です。大震災からもう4年も経つのですね。私は特に何をすることもできないので、「宗門の呼びかけ」に応じて二つのことをします。一つは追悼法要を行うこと。ですが特に大々的に法要を行えないので、朝課で追悼供養を一座勤めました。二つ目は地震発生時刻の14時46分に大梵鐘を9声撞くことです。被災地の一日も早い復興を願います。そして犠牲となられた尊い命に哀悼の意を表します。
曹洞宗報の以前の号に「菩薩に出会う」と題した随想が載っていました。福島県のあるご住職の文章です。一部紹介させていただきます。
『東日本大震災より一年半が過ぎようとしています。あまりに過酷な現実は人間にとって不条理の極みでした。納得できない苦しさは怒りとなっていつも胸の奥にあります。そんな中で菩薩のような人に出会うと、心の澱みが分解され、生きる光となります。 ・・・中略・・・ 津波の後、子ども二人と避難していた三十代の父親Yさんは、道路脇で果物を売っている女性に出会いました。こんな中でも商売かという思いがよぎりましたが、何も食べていない子どもたちのためにと思い、「おばさん、リンゴ三つ頂戴」と言いました。「三百円。その手提げ袋貸して」と言う女性に三百円と子どもの大きな手提げ袋を渡すと、女性は「ひとつ、ふたつ、みっつ、」とリンゴを入れ、続けて「みっつ、みっつ、みっつ、みっつ・・・・・・・・」と全部で十個のリンゴを袋に入れました。「子どものためだったら親はなんでもでぎる、頑張んだよ。」
恐怖の中、Yさんは温かい思いを胸に避難所にたどりつくことができました。』
Yさんはうれしかったでしょうね。手を合わせて拝んだことでしょうね。
自分のまごころから出た行為や言葉が、時として、相手に対しての菩薩となることがあります。
私も、この女性のような人に出会いたいと思うし、このような人になりたいと思います。
写真は、当寺の大梵鐘です。雲洞庵石龍禅師の銘が入っています。
布施というは貪らざるなり②
布施というは貪らざるなり。「独り占めしない」ということでもあります。
本山では食事の時に「生飯之偈(さばのげ)」を唱えます。
汝等鬼神衆(じてんきじんしゅう)
我今施汝供(ごきんすじきゅう)
此食偏十方(すじへんじほう)
一切鬼神供(いしきじんきゅう)
修行中はよく意味も分からず、ただ唱えているだけでしたが、大事な偈文だったのです。
「独占しない」ということについて、新潟日報の日報抄(2011.7.8付)を紹介させていただきます。
『仏教の作法の一つに「生飯(さば)」がある。食事の際に、ご飯の一部を取り置き、鳥獣などに施すのだという。食べ物を独り占めにせず、すべてのものに分け与える。そんな考え方が根本にあると聞いた▼先日テレビで曹洞宗の僧侶の食事風景を見た。1人当たり7粒のご飯が器に集められ、境内に寄ってくる小鳥に供されていた▼まねたわけではないのだが、拙宅の庭を遊び場にするスズメたちに数日前からコメを分け始めた。・・・(中略)・・・カーテンのすき間から観察して分かったことがある。彼らもまたわずかな糧を独り占めしない。一羽が数粒ついばむと、入れ替わりに別の一羽が舞い降りる。植木の枝には見張り役らしい一羽がとまる。誰に教えられたわけでもない。野性を生き抜く知恵だ▼3月11日夕から翌朝にかけて、津波から逃れた建物で、子供たちがポテトチップスなどを分け合って空腹をなだめたという記事が忘れられない。暗闇で小さなかけらをやり取りする光景を想像するだけで涙がでる。▼日本の食文化を世界無形文化遺産に登録する準備がはじまった。・・・(中略)・・・世界が注目するのは健康的で美しいところだという。しかし、私たちの食文化には、それ以上の価値があることが大震災で確かめられた。「独占しない」それは既に立派な無形の財産である。』
私はよく法事等の折に、祭壇に供えられた霊供膳の生飯(さば)を示して、この話しをさせてもらっています。「自分のものを分けてあげる」できそうでなかなかできないものです。ですが、さりげなくスッとできる人になりたいなと思います。
写真は、本堂壁の獅子の絵です。(本文とは関係ありません)