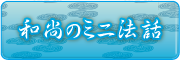和尚のミニ法話
五体投地 ですか?
頻繁に朝課参詣においでになるご門徒のAさんは、私のお拝姿が珍しいようで、以前「これは何ですか」とお聞きになりましたので、お拝の意味と仕草についてお話をしました。それを覚えおいでになったのでしょう。開山堂での諷経中に彼はお拝をされました。その姿は宗門のお拝姿とは異なり、インドやイスラムの方のお拝姿に近いものでした。まるで「五体投地」です。五体投地とは、五体(両膝、両肘、頭頭)を地につけてするおお拝のことです。考えてみれば、私らのしているお拝も原形は五体投地なのでしょうね。
彼がなぜお拝をしたのか、それは回向中に「A家先祖代々精霊に供養し・・・」と読み込みを入れたからだと思います。それがありがたかったのでしょう。
私はただ形式だけでお拝をしていることに気づかされ反省させられた朝でした。
写真:地蔵様コレクションより
「御朱印ください」の声が・・・
今日は春の陽気。雪が消えてくると外作務が気になります。アジサイももう大丈夫かと思い、冬囲いの板を外し始めました。例年より一か月早いです。やはり暖冬なんでしょうね。
気温上昇に伴い元気になるのは人間も同じことで、このところ「御朱印お願いできますか」という方が数人続いています。今日の方は歩いてお寺巡りをするのが好きだそうで、見附から歩いてこられました。当寺の御朱印にはアジサイのスタンプを押すのですが、気に入っていただけたようでした。このスタンプは、当寺の檀家さんから彫っていただいたものです。いわゆる消しゴムハンコです。とても好評です。ご希望の方は、どうぞ御朱印帳を持っておいでください。
写真:地蔵様コレクションより。地蔵様はいつも見ていてくださいます。苦しい時も、悲しい時も・・・。
閻魔大王は地蔵様?
昨日(2月8日)、「地蔵様の頭巾を縫う会」を行いました。11人からご参加いただきました。午前中の半日で頭巾と前掛けをたくさんこしらえてもらいました。
(その時の様子を写真を撮ったのですが、どなたかの顔がバッチリ写っているものばかりでしたので、ここにアップするわけにいかず、ウクライナ国旗の六地蔵様の写真でご勘弁を。)
さて、私たちがあの世に旅立つと、四十九日目に六道のどこに転生するかを閻魔大王がその判決を下すと言われています。六道とは、天上界、人間界、修羅界、餓鬼界、畜生界、地獄界の六つの世界のことを言います。この六道にお一人ずつ救いの仏がいる、それが地蔵菩薩です。ですから六地蔵なのです。このようなお話しから日本各地に地蔵信仰が広まっていったということです。
実は閻魔大王も地蔵菩薩の化身であると言われています。頭巾と前掛けを縫われた方々の善行修行は、閻魔様の目にとまっていることでしょう。
相手とともに自分を生かす
前々回に紹介した禅語「柳緑花紅」の続編です。本堂の襖にはもう一句「明月清風」とあります。春の禅語に対して今度は秋の語です。
この句は本来「清風拂明月 明月拂清風」(せいふうめいげつをはらい、めいげつせいふうをはらう)という言葉です。拂うは払うとほぼ同義と考えてください。秋のすがすがしい夜、風は月を払い、月は風を払う。つまり風と月はどちらが主体でどちらが客体ということはない。互いに主となり互いに客となっているというのです。互いが互いにいい影響を与え合い、時として一体となり時として個別になる状態とも言えます。さらに言えば、風と月は対立しあうようなものではありません。風が月を払いのけ自分だけの夜としない。と同時に、月は風を払いのけ自分だけ輝こうともしない。うーん、わかったようでわからない、まさしく禅問答!
敵か味方か、善か悪か、というような二元対立ではありません。自分の懐に相手を呼び込んだり、相手の懐に自分が飛び込んだりしながら自分というものを生かしていく。これが禅的な生き方なのです。とりあえず相手とともに生きるために「オレがオレがの【が(我)】を捨てて・・・」から始めたいと思います。