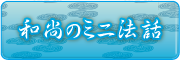和尚のミニ法話
お百度参りの数え札
今日から2月です。冬ももう少しでしょうか。1月は行く、2月は逃げる、3月は去る、と言われるように光陰矢の如し、あっという間です。
写真はお百度参りの数え札です。昭和初期のもので、隣家の先代の御内儀が寄進されたものです。札を一枚ずつ右にずらしていき数を数えるのに使います。当時は地蔵堂に掛けてあってお参り用に使われていたようですが、今はお百度参りの方はおられませんので不要気味です。除夜の鐘の時の数え札としてしか使い道がありませんでした。
ところが、最近新しい使い道ができまして。このところ毎朝のように朝課にお参りする方があって、その方のお参り回数に使っています。写真では上段札が8枚ずれていますが、今朝で10枚になりました。ご本人もお寺参りをする張り合いができたようです。この時期の5時半は寒いですよ。
「あるがままに生きる」と言うけれど・・・
中国宋代の詩人、蘇東坡は「柳緑(やなぎはみどり)花紅(はなはくれない)真面目(しんめんもく)」と詠みました。「春になれば柳の木は緑色の葉を揺らし、紅色に咲いた花は美しいばかりである。これぞ飾らない自然美である。この風景を本当の美しさとして感じよう。」というのです。作為のない真実とは「あるがままの姿に徹して生きる」ということに他ならないのです。「柳緑 花紅」という言葉は禅では好んで使われます。写真のように、当寺でも本堂の襖に大きく書されています。ありふれた日常の風景を美しいと感じ、自然界のすべてに支えられ生かされていることに気が付けば、幸せは手の中にある。
とは言うものの・・・・。わがままで執着心から抜け出せない凡夫(の私)は、坐禅を組んでも一向にその心境に達しません。まあそんなに簡単にいけば苦労はないのですが。坐禅会では、坐る姿がイコール仏の姿だとの宗旨に励まされている私です。
そんな気持ちで一首。『坐すれども 来し方のなお 離れざり 柳は緑 花は紅』 (駄首失礼:良秀)
仏壇や神棚がありながら無宗教って?
日本の大概の家には仏壇や神棚があります。新しく分家に出た家などはないかもしれませんが、アパートやマンション暮らしの方でも亡くなられた方がいれば(小さいながらでも)仏壇があります。
家庭の中に祭壇があるなんて外国では見られないようです。お参りは教会へ出向てするものだからです。詣でる対象は家の外にあるのです。
日本でも神社仏閣に出向いてお参りはしますが、毎日というわけにはいきません。「毎日お参りができるように仏様や神様を自宅にお迎えしたのが仏壇であり神棚である」という解釈を聞いたことがあります。俗っぽい説ですが本当のような気もします。
災害で家を亡くした方が、「小さくてもいいから新たに家を建てようと思うが、ちいさな仏壇を置くスペースは確保したい」と言われました。手を合わせる場所として必要不可欠なのでしょう。
一方、そんな仏壇や神棚のある家庭に居ながら「私は無宗教なので」と言う人がいます。私には?なのですが、仏壇や神棚と信仰とが結びついてないということでしょうか。
欧米とは異なるかもしれませんが、手を合わせる行為は、十分に信仰であると思います。
写真:地蔵様コレクションより。地蔵様は通常は錫杖(しゃくじょう)を手にされていますが、これは蛇の形の芴(こつ)ですね。
布施の原点かな
能登地震の義援金のニュースで、台湾の民間からの義援金が22億円を超えたそうです。親日国の台湾の人はいつも日本に心を寄せてくれてます。東日本大震災の時の義援金は官民合わせて200億円だったそうです。金額もさることながら、義援金に協力した町の人の声に感銘を受けました。それは、「台湾には《あげる方は 受け取る方より もっと幸せ》ということわざがあります。私の僅かなお金が被災地の幸せになり私の幸せになるのです。」という話しでした。
このことわざはまさしく布施の原点といえるのではないでしょうか。日本ですと、もらう方は「申し訳ない」という感情が沸き起こりますが、台湾の方はたとえもらう側であっても、相手を幸せにしているから私も幸せと感じているのではないでしょうか。あげる方は威張る必要はないし、もらう方は卑屈になる必要はないのです。
托鉢もそうですね。雲水が来るのを待ち構えて浄財を入れてくれる方の嬉しそうな笑顔を何人も見た覚えがあります。
写真:地蔵様コレクションより。
凡人の一句 「大寒や 黙然不動の 笠地蔵」(良秀)
中田の観音様と光照寺
昨日のミニ法話に載せた写真は、会津の「ころり三観音」の一つである中田の観音様と呼ばれる弘安寺の本尊様です。この弘安寺様と光照寺は少なからず縁がありまして。
数年前、当寺の土蔵を整理していたら古い書状の中に見つけました。当寺20世黙堂碩淳大和尚は弘安寺から光照寺へ転住(てんじゅう:住職の転勤のようなもの)されたことがわかったのです。私は先住から何も聞いていなかったので、その時とてもびっくりしたことを覚えています。そして、弘安寺も光照寺も山号は普門山で同じです。どのような因縁だったのでしょう。そう言えば、近所の檀家さんに観音様の掛け軸があって「弘安寺碩淳」と名が入っていました。お盆の時にこの掛け軸を精霊棚に掛けるのです。ご当主はまだお若いので、その由来はご存知なかったので、弘安寺とのつながりをお話ししたことがありました。
碩淳和尚の苗字は菊池です。ここから光照寺の菊池が始まります。21世榮淳和尚は長岡の長谷川家から養子に入り菊池となり、その子が22世の碩榮和尚(先住)、さらにその子が23世の私です。
このようなご縁があるので、弘安寺の観音様のポスターは、数年経ていますが片づけられません。
写真:地蔵様コレクションより。流木を使用して六地蔵様の台にしています。