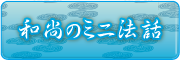和尚のミニ法話
永代供養墓前庭改修1
生きつくす
「・・・つくす」というとどんな言葉を思い浮かべますか。
「食べ尽くす」。テーブルのものをきれいさっぱり全部食べてしまうさまです。出された料理を全部平らげてくれると作った方は嬉しいものです。
「語りつくす」。いろんな思い出話を余すところなく話切るさまです。友人と夜を徹しての話は友情をさらに深くしてくれます。
全部、残さず、きれいさっぱり、余すところなく・・・ そんな感じです。
先日、98歳のご老婦人の葬儀に参りました。
喪主さんのお話では、このおばあさんはずっと元気で過ごされておられましたが、一週間ほど前から食事ができなくなり、口からものが入らなくなりました。しかし苦しむこともなく、痛がる様子でもなく、すー、すーと静かに呼吸されていましたが、その呼吸もだんだん弱くなり、やがてロウソクの灯が消える如くすーっと息が無くなりました。
老衰ということですが、これこそ大往生でした。息子さんである喪主さんは安心して見届けることができたとおっしゃっていました。
まさに「生きつくした」終いだったようです。
お釈迦様からお借りしたこの命を、98年間にわたってまさに生きつくされました。お釈迦さまもご満足であろうと思います。
「生きつくす」ことはなかなかできるものではありません。病気や事故、災害、等で「生きつくす」ことができずに亡くなる方がほとんどのご時世です。自分だけがそう願っても叶えられないことが多いようです。
「生きつくす」のに支えとなってくれたご家族、施設の方々等々のご苦労も忘れてはなりません。
私は、自分の人生を「生きつくす」ことができるかわかりませんが、せめて今日一日の命を生きつくしたいと思います。
彼岸花
今日は彼岸の入り。ちょうど時期をあわせたかのように、あちらこちらに彼岸花が咲いています。
彼岸花は不思議な花ですね。彼岸になると忘れずに必ず咲きますもんね。今年は長雨だったからいつもより遅くなるとか、晴天に恵まれて早く咲くとかなくて、どんな天候でも彼岸になると咲きます。自然の摂理なのだろうと前から思っていました。ところが、今日はたと気が付きました。彼岸花は、仏様の「おーい、そろそろ彼岸だよ。到彼岸の修行の用意はいいかい。」とのお告げを伝えるためにこの時期に咲くのではないだろうかと。
「彼岸イコール墓参り」みたいな習慣ができつつありますが、本来の彼岸の意味は彼岸に到る六つの徳目(六波羅蜜)の実践強調週間なのです。
彼岸花は曼殊沙華とも言いますね。字面からしていかにも「仏様からのお遣い」のようですよね。
「きょういく(教育?)ときょうよう(教養?)
「若いころと違って年をとると体はきかなくなってくるし頭は弱ってくるし・・・。特にすることもないもんだから一日中テレビを見たりボヤっとしていることもあって、ボケなきゃいいけど。年は取りたくないもんだね。」高齢の方との話でよくでてくる話題です。
こんな話を聞きました。「年をとってから大事になるのが「教育」と「教養」です。教育は『今日行く』、教養は『今日の用』のこと。つまり、今日行く場所があって、今日する用事があること。この二つがあれば簡単にボケることはありません。」
なるほど!うまいこと言うもんですね。畑仕事や田んぼの仕事のある人や趣味のある人はいいですが、することのない人もいるようで、家にいると邪魔扱いされるので、市の図書館に行く人も大勢いるようです。中には開館時間前から並んで待っている人もいるとか。男の方が多いようです。「今日行く」場所がないから図書館で暇つぶしなのか、一日中新聞を隅から隅までじっくりと呼んでいく人もいるとか。その方にとっては重要な「今日行く」と「今日用」なのでしょう。
私の一日は、朝は5時に本堂に行って暁天坐禅と朝課。粥罷(朝食後)は檀家さんの月参り。帰山してから薪割りや草取りの外作務。夕方晩酌してさっさと寝る。これが私の「今日行く」と「今日用」です。僧侶はありがたいですね。やることがあって。雨の日は外作務ができなくてちょっと困っています。(冬になれば雪かきができるのですが)
法事の法話でときどきこの話をします。「皆さん、今日法事に来れてよかったですね。行く場所もあったし行く用事もあったしね。」と。
○○坊主
「〇〇坊主」という言い方はたくさんありますね。乞食坊主、てるてる坊主、なまぐさ坊主、海坊主・・・。
大本山永平寺発行の「傘松」には毎号安居者(修行僧)の随筆が載っているのですが、今月号のR禅兄の随筆の冒頭にこうあります。
『「どんな僧侶を目指したいのか、考えながら修行に励みなさい。」僧侶には色々あり、坐禅を主とする「坐禅坊主」のほかに「作務坊主」「諷経坊主」「説教坊主」「梅花坊主」「葬式坊主」「修行坊主」等々たくさんの例を挙げながら師匠が話してくれました。・・・後略・・・』
うーん、それしかしないというのではなく、得意とするところ、という意味の〇〇坊主なのだと思います。確かにT寺の先代方丈様は「坐禅坊主」でしたしS寺の方丈様はお話がうまくてわかりやすい「説教坊主」です。SA寺の先代方丈様は御詠歌がべらぼうに上手でしたので「梅花坊主」でした。
自分のことに当てはめてみると、どれもそこそこできるけどこれといった得意技のないのが私です。しいて言えば、話はまあまだと思いますが、寺族からは「長い!」と不評を買うこともあります。今は「作務坊主」でしょうか。薪ストーブ用の薪づくりや挿し芽で増やしたアジサイの定植、ときどき草取り。今は外作務に精を出しています。(なまぐさ坊主は昔から変わりませんけどね。)