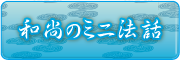和尚のミニ法話
菩薩に出会う 3
ちょっといい話を新聞で見つけました。4月2日付け新潟日報「窓(投書欄)」より抜粋。
タイトルは「進んで手貸す子うれしい」『先日、市内のアイスクリーム店に行きました。注文し終わると若い父親と3人の男の子たちが入ってきました。(中略)私が家族の分もアイスクリームを受け取り出ていこうとしました。ドアの前で思わず「あっ」と声が出ました。ドアノブを回さないと外に出られないのです。両手にアイスを持ったままではドアノブを回せません。その時です。男の子の一人が素早く状況を察知してドアを開けてくれたのです。誰かに言われたからでなく、困った人がいたら進んで手を貸すことができる。そういう子に出会え、本当にうれしかったです。(後略)』
この男の子も菩薩様です。子供だって菩薩様なんですね。修証義に曰く、「・・・自未得度先度他の心を発すべし。この心を発せば七歳の女流なりとも四衆の導師なり。衆生の慈父なり。男女を論ずることなかれ」と。自未得度先度他(じみとくどせんどた)とは、自分は後回しにして他の人の幸せを先にしてやることです。
相手の幸せのためにスッとさりげなく行動を起こせる人はまさしく菩薩様です。きっと店にいたみんなの心が温かくなったことでしょう。
写真は本文とは関係ありません。当寺の永代供養墓と地蔵堂です。
「おまえもな」ではなく「おまえこそな」でした
新型コロナウイルスの感染が止まりません。どうなってしなうのか心配です。月参りのお茶飲み話はもっぱらこのことばかりです。
あるお宅で言われました。「方丈さん、あなたこそ大丈夫なんでしょうね。私は外出しないようにして家にばかりいるけど、方丈さんはいろんなお宅に行くし、多くの人と会っているのだから・・・。」
言われてみればその通り。月参りの話し相手はお年寄りが多く、彼らにしてみれば私の訪問は心配のタネですものね。
マスクの効用がいろいろ言われていますが、自分が感染を広げないようにしなくてはなりませんので、お経もマスク着用ですることにしました。(でも息苦しくて大変ですが)
写真は、庫裏玄関の標示札です。アルコール消毒液が手に入らないので、来山者に手洗いをお願いしています。
開花宣言
いつもと違う春彼岸
菩薩に出会う 2
地蔵様は菩薩様です。菩薩とは人間に非常に近い存在で如来様のもとで衆生済度の修業中とされる存在であります。
私たちの身の回りにはまさしく菩薩様ではないかと思われるお方がおられます。「菩薩に出会う」と題してお話しします。(第1回目は2015年3月11日の記事参照)
3月13日付けの地元紙三条新聞の読者投書欄にいいお話が載っていました。抜粋して紹介します。
『先日ありがたいことがありました。トイレットペーパーが今使用している分でなくなるので買いに行きましたがスーパーも薬局もどこも売り切れ。困りながら店を出たところ、ある男性の車にトイレットペーパーが積んでありましたので思わず見つめてしまいました。その男性が「トイレットペーパーかね?」と話し掛けてこられたので、私は自分が一人暮らしで徒歩でしか買い物ができないなどのことを伝えると、男性は自分のトイレットペーパーの袋から6個取り出して私の手押し車のカゴに入れて「これでしばらくは大丈夫でしょう」と言ってそのまま走り去りました。こんな誰にも相手にされない老人に手を差し伸べてくださりありがとうございました。お金も受け取らずお名前もはぐらかされてしまいました。このご恩は忘れません。』(「長岡市・77歳のおばば」さん)
投書の主さん、よかったですね。まさしく菩薩に出会うとはこのことですね。私もこのような菩薩になりたいなと思います。
(私も出会っているのかもしれませんが、心の持ちようで菩薩と感じられないでやり過ごしていることがあるかもしれません。)
写真 : 地蔵様の頭巾と前掛けをつけ代えました。彼岸ですので。